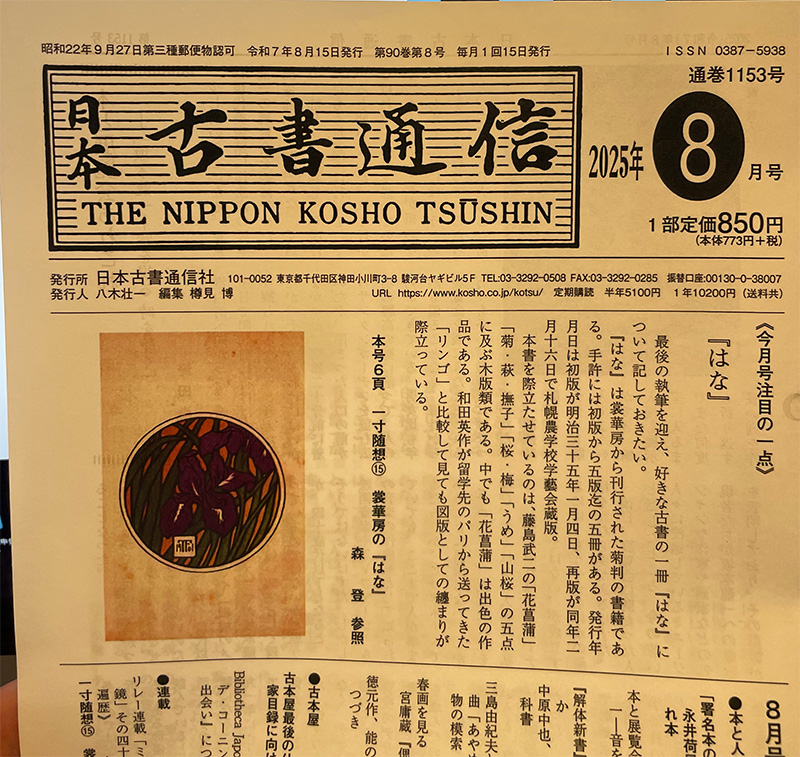野田尚稔さんが日本古書通信の2025年8月号(通巻1153号)の『本と人』というコラムに「本と展覧会あれこれー「坂本龍一音を視る 時を聴く」」と題して文章を書いています。ご本人から抜粋でコピーをいただきました。
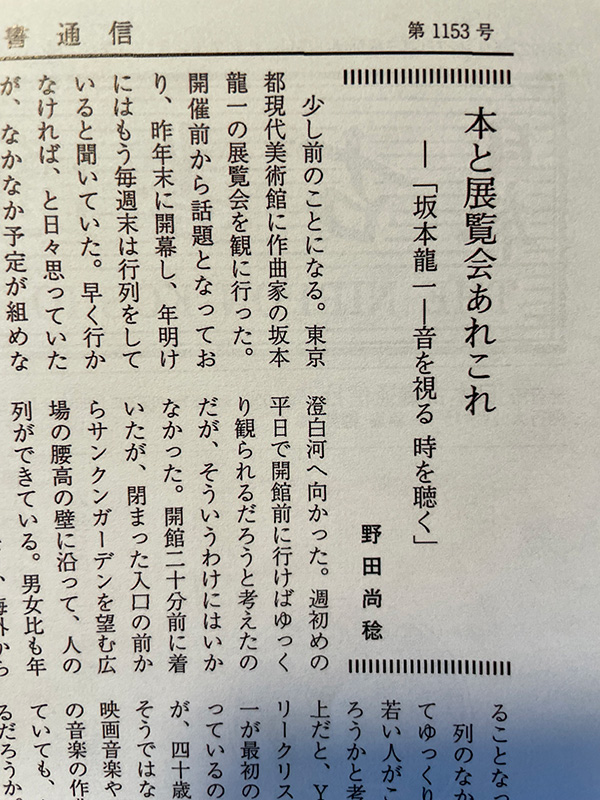
野田さんは、2010年に世田谷美術館と三重県立美術館で開催された『橋本平八と北園克衛展』で世田谷美術館の学芸員として北園克衛の展示を担当された方です。最近では、世田谷美術館が発行する紀要に若い頃の北園克衛の書簡を積極的に紹介しています。
北園克衛は、現在の詩の世界では脇道に外れた存在として、視覚的な詩の表現のことを除き、取り上げられることはあまりありません。詩の世界ではなく、むしろグラフィックデザイナーが活躍する視覚表現の世界で北園克衛の業績が評価され、現在も影響を及ぼしています。
北園克衛の詩は、言葉を雑音のない静かな部屋に置いて、単なる記号として扱い、視覚的なものを頼りに世界との関係を再構築するもので、いわゆる言葉が喚起するものとは違ったことを「詩」として提示するものでした。それゆえ詩が表現する抽象的で感覚的な言葉、あるいは詩が表現する意味を含有したものといった言葉の芸術では捉えきれない感性を、読む人に強いることになります。そうなると、言葉の世界で通じ合うことや新しい言葉による表現を模索することがばかばかしくなってくる。そんな面白味のない詩の世界を北園克衛の詩に感じてしまうことがあるのかもしれません。
例えば、その時代、プロレタリアートな詩、シュールレアリズム影響下の詩、アナキズムな詩など。時代と拮抗した表現が激しく主張をしていましたが、北園克衛は時代というものに対して極めて冷静に対峙したかのような純粋な表現を好みました。そういった嗜好は、まだ誰も書いたことがない詩の表現を模索する意識につながっていると思います。1920年代に日本におけるモダニズムの詩の最先端を走っていた詩人たちの中では、様々な詩の雑誌が創刊されては消えてゆきました。それは、何か新しい動きが始まる前夜のような、歴史的な瞬間が若い無名の人たちによって刻まれる様子でもあります。
文章は、世田谷美術館が『橋本平八と北園克衛展』を開催しているときに、ある美術館の学芸員が「坂本龍一が北園克衛に関心があるから観にくるかもしれないよ」と言ったことに端を発し、野田さんの北園克衛と坂本龍一との繋がりに関する楽しそうな想いが語られています。
坂本龍一の二つの展覧会、2017年のワタリウム美術館での「坂本龍一 設置音楽展」と2025年の東京都現代美術館での「坂本龍一 ー音を視る 時を聴く」展で制作にインスピレーションを与えた書籍として、北園克衛の『白のアルバム』が収まられ展示されていたことを確認できたときの気持ちや、内堀弘『ボン書店の幻』に描かれている『マダム・ブランシェ』創刊時の北園克衛と岩本修造の関係の構図が、YMO結成時の坂本龍一と細野晴臣になぞらえて語られる場面を楽しげに思い出しています。
北園克衛の詩に魅せられたものの一人として、とても楽しい読み物でした。